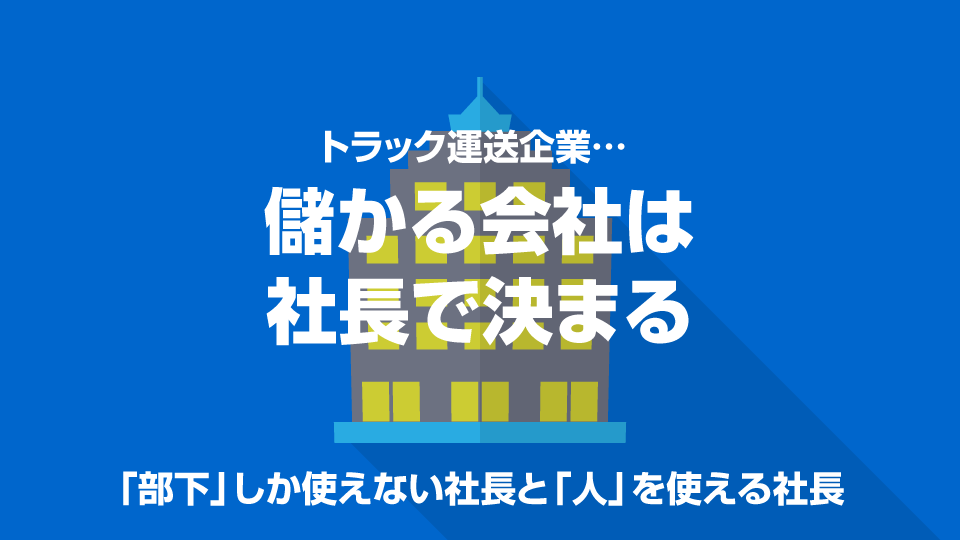大企業に働く多くの社員は、大企業という会社自体にロイヤリティを持っている。それに対して中小企業では、経営者(たいていはオーナー経営者)に対して何らかのロイヤリティを持っているから、その会社で働いているという傾向がみられる。また、会社にも経営者にも何のロイヤリティもなく、会社も経営者もいやだが、比較的給料が高いので生活の糧を得るためだけにその会社で働いている、という人たちも存在する。これは自分の生活に対するロイヤリティといえるだろう。
ところが最近は、企業に対するロイヤリティでも、経営者に対するロイヤリティでも、生活のためだけでもない、という人たちが増えつつある。経営者は、このような人たちの能力も活かすことができるようにならなければいけない。
現在では「一生懸命」と書くのが普通になってきた。そもそもは「一所懸命」だったのである。ところが一生懸命と書く人たちが増えてきた。そこでどちらでも良いことになり、さらに現在では一生懸命が一般的な表記になってきたのである。
国語辞典などを昔から今日まで出版された年代順にみていくと、そのあたりの経緯が分かる。そして今では、一所懸命を知らない若い人がいるかも知れない。
ところで、辞書などによれば一所懸命は領主から与えられた領地で、頑張って必死に生きるなどという意味とされている。まさに封建社会という時代においては、的確な表現の言葉だったと言える。
そのような観点から見ていくと、戦後の日本の経済成長の時代は一生懸命よりも「一社懸命」の方が的確な表現なのではないだろうか。とくに大企業では一つの会社で定年まで勤め抜いて、必死に生きていくということである。
だから、入社して最初の配属は本社の総務部門であった。その後、地方の営業所に営業職として転勤になり、本社に戻って人事部に勤務、次は工場にでて生産管理をし、本社の業務部、さらに地方支店で管理職、再び本社に戻って云々…。そして上手くいけば役員になり、やがては社長にまでなれるかも知れない。あるいは最後まで会社に残ることができなくても、子会社の取締役に就任し、子会社で社長になる可能性もある。いずれの場合でも、最初に入社した会社の傘下(領土内)で一生を過ごすことになる。
これはまさに一社懸命そのものではないだろうか。先の会社に対するロイヤリティの典型である。そして終身雇用制度と年功序列賃金体系、企業内組合などが、一社懸命の背景にあったのだ。
それに対して中小企業では、オーナー経営者に対するロイヤリティが大きな要素を占めることが多い。
ところが大企業という会社に対するロイヤリティでもなく、中小企業のように社長に対するロイヤリティでもなく、あるいは生活の糧を得るということに対するロイヤリティでもない生き方が日本でもでてきた。それは、職業に対するロイヤリティという生き方である。専門的な職業では、従来もなかったわけではないが、最近では職業に対するロイヤリティで働くような人たちが増えてきたように感じる。
たとえ多くの人たちが羨むような大企業に入社しても、自分がやりたい仕事ができる部署に配属にならなければ辞める。そして自分がやりたい職業を貫くためには、どのような会社かにはこだわらない、という生き方である。これは「一職懸命」な生き方と表現することができる。
この一職懸命という生き方を象徴するものの一つに専門職の派遣労働がある。専門職で派遣労働という就業形態を望む人は、企業にはこだわっていない。自分の職業、専門能力に対するロイヤリティなのである。このような専門職で派遣労働を希望する人たちのマネジメントを代行するのが、本来の派遣会社である。
日本の場合には単に人件費の削減だけを目的に、単純労働においても派遣労働者が活用されている。単純労働の派遣会社は、いわば現代的な「手配師」のような性格になってしまい、社会的な諸問題を惹起した。しかし、本来の派遣労働は一職懸命な生き方を望む人たちのマネジメント会社なのである。
ついでながら一職懸命と一生懸命が合致するような人生が、一番幸せな生き方といえるだろう。
それはともかく、人には様ざまな生き方がある。これまでの多くの社員が一社懸命だったからといって、現在も、さらにこれからも同じような認識でいると、多様化する社員を使うことはできなくなる。多様な意識や生き方の社員を使っていくには、部下を使うのではなく人を使うことのできる経営者にならなければならない。
部下はだれでも使うことができるが、経営者は人を使えなければいけないのである。